3大高級魚の一角、シロクラベラ
こんにちは、夢海です🐟️
24年秋のこと。暑い暑い夏日の中、涼しい豊洲場内を彷徨い歩いていたいつも通りの日のこと。
さてさて今日はどんな子に出会えるのかなと高揚する気分はいつも通り、市場に入って数店舗目でこの鼓動は一気に早まります。
この日は時間がない。なんて慌ただしく歩き回りながら、とりあえず晩のおかずが確保できればいいや。なんて考えていました。
この日最初に足を止めたのが、見慣れない長い発泡に入れられて並んでいた大きなメガネモチノウオ。
おそらくは5キロほどと大きくなる魚のうちでは大きすぎず手頃なもの。うおお!いいな、買おうかな。
なんて思いながらふと横に目をやると、そこにはクリーム色の魚がゴロリゴロリと大量に並べられています。
「いやいや長いこと探し求めていたのはこっちでしょう。」
ということで、大きめのものを1尾選って頂き、これを買ってきました。
目次
シロクラベラの特徴

今回の魚は、マクブこと標準和名シロクラベラ。
クリーム色に近い白く品のある体色をベースに、装飾品を思わせるような青い色が体に散らばります。
本種は沖縄で三大高級魚とされるもののうちの一角であり、産地も沖縄のものとなります。
三大高級魚とされるのがスジアラ(アカジンミーバイ)、ハマダイ(アカマチ)、そして本種シロクラベラ(マクブ)の3種となり、前2種は沖縄以外でも水揚げがあり、これが豊洲へも入ってくる為、値段さえ気にしなければ入手は容易です。
しかしシロクラベラは産地が琉球列島などのみと限定的。
沖縄方面からの水産物は多くはやって来ないため、関東で食べようと思ってもなかなか見つからない魚となります。
そんな3大高級魚の残り一角であった本種をようやく見つけて買えた、という事になります。

そんなシロクラベラですが、ある程度魚を見る方になら、分類は分からなくとも体型がどのかあの魚に似ている。と気が付くのではないでしょうか。
本種は名前の通りベラ科魚類であり、更にはイラ属であるためで、温帯な海域に多く、長崎などから入ってくるイラとはまるで色が違うだけのように見えてくるほど輪郭がそっくりです。

青っぽい斑点が体の後部に散らばるなど、模様も何処となく類似性が見られます。
さて、シロクラベラに話を戻します。

青い斑点は体の後方にいくにつれて線のように連なっていく。

臀鰭の模様は、根元を青色ラインが通るというベラ科らしい配色です。

背は黒斑があり、これはまだ若い個体に見られるもの。成長とともに消える。

このまま残しておきたい、と思えるほど見惚れる美しい魚ですが、そういう訳にはいかないので観察は程々に、卸していきます。
卸すと真っ白の綺麗な身が現れます。

身は膨れ、体の厚みがある魚であることを改めて認識させ、さわった感触もしっとり滑らかな、まるで魚の絹であるような質感。
脂がすごい!という魚ではないものの、密度の高い身で包丁が途中で重くなる感覚がありました。

刺身は尾に近いところを。
他は調理前に切りつつ、じっくり食べていきます。
シロクラベラの料理
シロクラベラの刺身

初日は刺身で。
一部背の身を焼き霜にしました。
まずはそのままのもの。
脂が少しだけあり、微かに醤油をはじきます。
噛むほどに味が出てくるようなもので、同属のイラと比べると圧倒的に味がある。ように感じられます。
シロクラベラの握り

続いては握り。
せっかくの魚なので食べ方を色々と研究するべく、単につけたもの、湯引き、焼霜の3つでつけました。

そのままつけたもの。
これは無難な美味しさで、白身という枠に当てはめれば、質はとても良く、しこっとした身はシャリとの馴染みも悪くないもののやや旨味に欠ける。というよりインパクトが薄い。
一方で湯引きになると、身が引き締まりプリンっという食感になると共に、ベラというよりはフグ類に似ている。という感想が浮かんでくる。
本種が取れる海域ではフグは居ても小型で有毒か、身が少なく生食に適さないアバサー(ハリセンボン類)ぐらいしか獲れない事を考えると、本種のような質の白身というのは希少で、ネタとして1つ欲しいようなものなのかも、と考える。
ここの疑問点もいつか来るであろう沖縄遠征の時に確認する事項として、ひとつ覚えておきます。

最後に焼霜。
南方のベラやブダイは特に皮に特有の香りがあり、これはシロクラベラもやや感じられはしたものの嫌味のない、上品さのある隠し味のような風味程度で収まっている。
しかし皮は厚い上に火が入ると縮こまるので、焼霜にはそれほど適さない模様。
湯引きの方が美味しいかもしれないな。
少し硬いというか、尾に近いと筋が強いので硬く感じられてしまう点で言えばシャリとの馴染みがイマイチだと感じられてしまいますが、握りは総じて評価は高めです。
シロクラベラの天ぷら

2点目は皮付きで縦に切りつけて天ぷらに。

皮を引いてもよかったものの、特色を出すためにも皮は残しました。
この皮に香りがあり、これがないとかなりあっさりとした白身で面白みに欠けてしまう気がします。
身はしとっとして、ボソっとした感覚はありません。
シロクラベラの西京焼き

頭部に近い部位は西京焼きに。
西京味噌に漬け込み、冷凍庫で一時保管。
純白色の身が味噌で染まり、いい感じに浸かったなというところでワクワクしながら焼き上げます。
わざわざ沖縄の魚を味噌につけて焼こう!という事をしている人は滅多にいないので、ある意味貴重な1品でもあります。

とても亜熱帯域の魚とは思えないキメの細かさ、焼くことで顕著になり脂の香りも感じられる。
それこそ沖縄の魚でいえばフエダイ科のものなどと張り合えるのではないか。なんて思えるほど、味がしっかりした上で嫌味がなく食べやすい1品です。
シロクラベラの評価
価格 ・☆☆☆☆
コスパ ・・・・☆
珍しさ ・・☆☆☆
味わい ・・☆☆☆
・価格
沖縄などの産地の魚ではトップクラスで高い値が付く。ベラ科で考えてもはメガネモチノウオと並び非常に高価なもの。
・コスパ
単価に対して歩留まりは普通。体高があり身はふっくらとしているが、頭の大きさはやや目立つ。
・珍しさ
関東では珍しい。
・味
刺身でよし、焼いてよし。南方の磯魚のような癖がなく、生食でも当然美味。使い方によっては味気なかったりする為、皮を活かして上手いこと使いたい。イラに比べて味わい深い。
今回は3大高級魚のひとつ、シロクラベラを頂きました。
今回は生食を中心に色々試してみました。
この魚の真骨頂は、火を通すとさらに上物の白身であることがより分かるものだと思います。
購入から度々見かけてはいるので、またお金が貯まったら買おうと思います。

副管理人:夢海 未利用魚の有効活用方を探して、様々な魚種を食べて美味しく食べられる方法を研究しております。今まで550種以上の魚類を食べてきました。変わった魚の食べ方を中心に公開させて頂きます。どうぞよろしくお願いします! Twitter: @YUMEUMI27 ブログ: 夢海のまったり魚日記
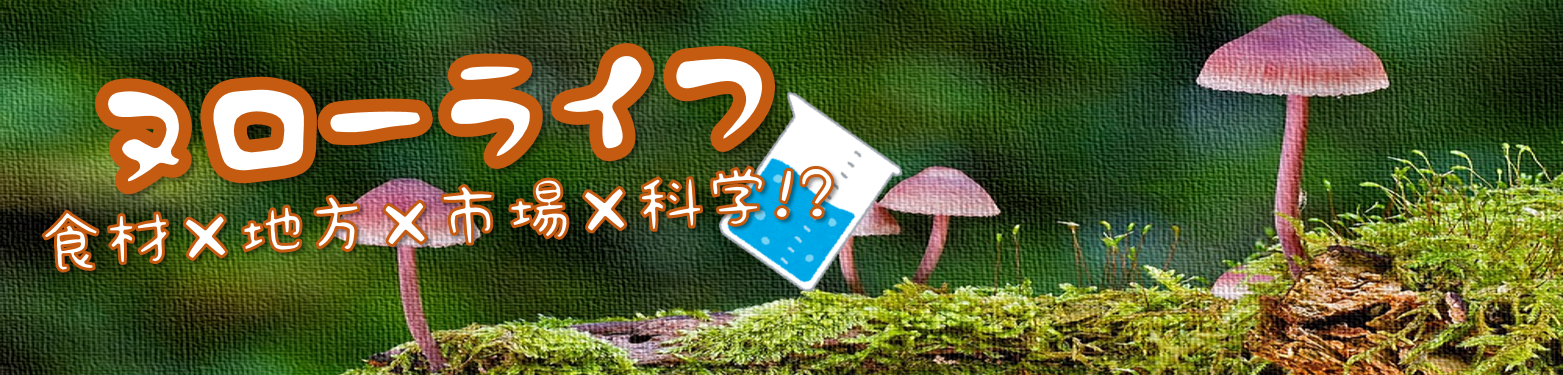


ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません