珍魚を食べよう!ネズミギンポ
こんにちは、夢海です🐟️
2024年は市場では手に入りにくい、産地周辺で出回る魚を求め津々浦々各地から魚を取り寄せるという事が多い年となりました。
今回の魚は北海道羅臼から来たもの。
初めて頼むところなのにアレコレお願いをし、まとまって揚がったら送るよ!と言っていただいた数日後。
初めてのもの盛りだくさんでオホーツクの魚がやってきました。
今回のその中からネズミギンポという魚を紹介します。
目次
ネズミギンポの特徴

ネズミギンポはタウエガジ科に属する、上越・東北以北からベーリング海などにかけて北に広い生息地を持つ魚で、今回の個体は全長32.0cm、128gと細長さ故に小さく見えるが、平均的なサイズでした。
由来は分かりませんでしたが、名前の様にねずみ色を思わせるような暗いグレーに、細長い体つきが特徴です。

口は下向きについており、上顎よりも鼻先が前に出て尖った顔つきです。
胸鰭は黒く、体はまだら模様が全身を覆います。

背鰭は大きく、棘条がビシッと連なり、素手で握ろうものならかなり痛い思いをします。

尾鰭は黒く団扇型。
タウエガジ科では比較的一般的な姿形ですが、関東に住んでいる人間にとっては身近ではない見た目で、見るほど引き込まれるような感覚になります。
ネズミギンポの料理
ネズミギンポの握り

まずは握りから。
肛門のところで2つに切り分け、尾に近いところの半身を降ろします。
これの皮をひいてつけるだけ。

見た目はピンク色で美しく、血合いの入り方や色味はどこかサメ類のような質にも見えます。
皮目が滑らかでなんとなく脂っぽさがあり、期待半分で食べてみたところ、旨味は薄くほぼ味がないものでした。
北の魚にしては珍しくヌメリや体表にもにおいが少なく、身までもクセがありません。
しかしあまりに淡白過ぎるというか、単純過ぎる味わいで味としては印象に残りにくい。
シコッとした食感があり、昆布締めにする、皮を炙るなどすると特色が現れるでしょう。
ネズミギンポの干物

ネズミギンポを肛門のところで切り分ける。
頭に近いところは骨付きで開く、内臓を取り洗う、塩水に漬ける、これを冷蔵庫で干して表面が乾いたら焼き上げる。
類似した干物が思いつかないような見慣れない魚ではあるものの、元が黒い魚なので焼きあがりの見た目はおいしそうに感じられます。
脂は皮目にのみ感じられ、焼きあがりは表面から泡が吹いています。
塩によって引き締まった身に、見た目以上にほわっとした膨れる優しい口当たりの繊維から旨味が拡散され、嫌味のない上品な味わいなのに表面の脂で香ばしく焼けた皮がアクセントとなり、おかずにもつまみにも広く適用できる優秀な味となります。
大きさもちょうどよく、1尾もあれば一食のおかずにちょうど良いと感じられます。
身の質感などは同科で唯一食べたことのあるナガヅカに似た印象を覚えました。
ネズミギンポの評価
価格 ・・・・☆
コスパ ・・・☆☆
珍しさ ・☆☆☆☆
味わい ・・☆☆☆
価格
・底引き網などの混獲であがり、細かい上まとまらず市場価値はほぼないもの。基本的には市場で目にすることはない。
コスパ
・小さい上に細長い魚体のため可食部は限られる。調理法は開き干し、から揚げなどに適する。
珍しさ
・流通上では一般にみられないので非常に珍しい。市場など水産の世界での入手は極めて困難である。
味
・北方の魚の中では独特の香りがなく食べやすい。身に含まれる水分も多くなく、締まった筋肉で調理用途も選べる。
今回は羅臼から来たネズミギンポを調理、実食してみました。
小型な魚のため調理に手間はかかるものの、一夜干しや天ぷらなどのネタにしても味があり美味いつまみになりそうな魚です。
特有の香りがある魚が多い北国のものの中では比較的抵抗なく使える。そんな印象です。
今回は2品しか作れなかった為、美味しいであろう天ぷらやフライなどを筆頭に、次回は揚げる調理方を試してみたいところです。

副管理人:夢海 未利用魚の有効活用方を探して、様々な魚種を食べて美味しく食べられる方法を研究しております。今まで550種以上の魚類を食べてきました。変わった魚の食べ方を中心に公開させて頂きます。どうぞよろしくお願いします! Twitter: @YUMEUMI27 ブログ: 夢海のまったり魚日記
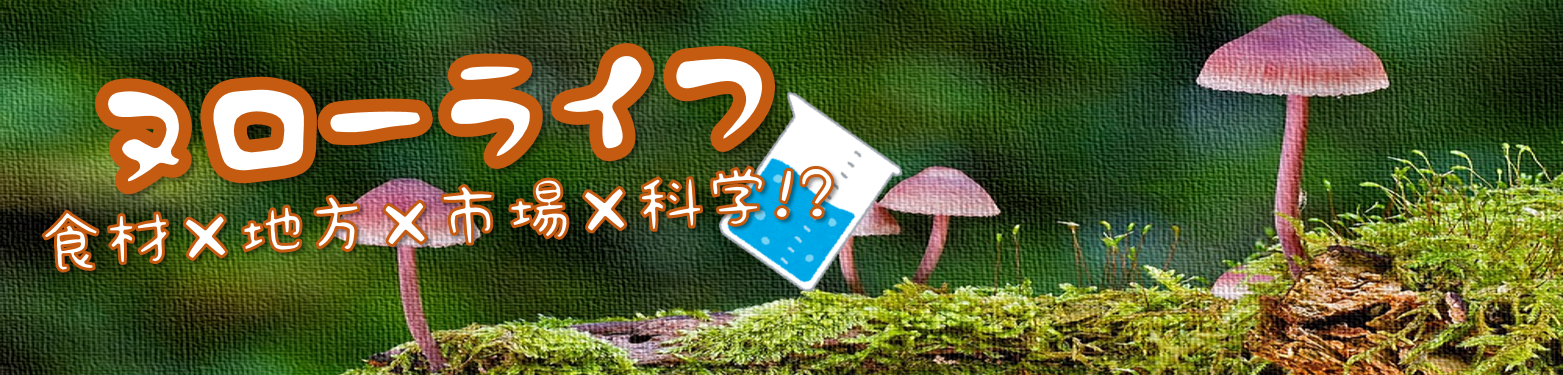


ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません