ブダイ1美味しいのは誰だ!?ナンヨウブダイ
こんにちは、夢海です🐟️
沖縄の鮮魚が…というより、今年も行けず毎年沖縄を恋しく想っている今日この頃。
沖縄に限らず、鹿児島にすら行けておらず、思えばここ1年で訪れた最南端は大分県佐伯であったのではないかと思い返します。
つまりは温帯の見慣れた海、魚を探し求める毎日こそが刺激ですが、さらにテイストを変えて彩り豊かな亜熱帯海域の魚たちを今欲していると強く思います。
今回の魚もまた沖縄から鮮魚セットを取り寄せた際に入っていた内容のもので、正直この魚が入るとは考えてもみませんでした。
目次
ナンヨウブダイの特徴

今回の魚はナンヨウブダイ。
発泡を開けると何やらエメラルドグリーン色の巨大魚がいる!!とそ~っと蓋を開け、現れたのは巨大なナンヨウブダイ。
ちょうどこの前後でブダイを調べる機会があり、ナンヨウブダイいいなぁ。と図鑑の写真を眺めていました。

恐らくは海中で銛で突いて漁獲されたものでしょうか。鰓の後方のところに突いた跡であろう穴が見えます。
ここを見事に狙い撃つのはさすがはプロ、といったところです。

ブダイの仲間は英名で「Parrot Fish」と呼ばれ、そのままオウムの魚となります。

オウムに似ているのは嘴のような剥き出しの頑丈な歯と共に、小さく丸い瞳孔を持つ目もまた鳥に似ているように思えます。
おまけに多くの種が色彩豊かなカラフルな見た目をしているので、魚で最もオウムに容姿が似ている種類と言えます。

腹鰭は青色がエメラルドグリーンを縁取ります。
まるで外洋にポツリ浮かぶリーフを思い浮かべさせるような色合いです。


尾鰭の縁もまた鮮やかな色で、尾鰭後縁の浅い珊瑚礁の色合いは引き込まれるような魅力があります。
尾鰭は上葉・下葉が延伸します。


下ごしらえは大きな鱗をバリバリバリと豪快に落としていき、鱗も調理に使うためにかき集めておきます。

腹が膨れていたのはこの浮袋と巨大な肝が入っていた為でした。
南方の魚、それも珊瑚礁などに生息する魚の肝は有毒の可能性もあるので、一般には無毒魚とされるものでも食さない方がいいでしょう。
色味も綺麗でたたいて刺身に絡めて食べたり、汁に入れても美味そうな見た目ですが、命大事に。ここはグッと我慢です。

胃袋が破れてしまいまな板に散らばった内容物。
ブダイはサンゴや岩をガリガリ削り取り、細かい砂になった糞を出すという食性をしています。
珊瑚礁域で漁獲されたブダイ類の内容物からは甲殻類やウニなどの破片が出てくることも多いです。

卸した身はザ・南国魚。真っ白で濁っています。
同年に捌いたシロクラベラも似て、水分が少なくしっとりした感触。
当然、触っても脂が感じられるなんて事はなく、随分とあっさりした質です。


↑寝かせておくために乾燥防止で巻いておいたペーパーが青色に染まっていた。
こういった魚から色素を取り出して天然の着色料を生成しても面白そうだと考えました。
ナンヨウブダイの料理
ナンヨウブダイのお造り

まずはお造りから。
青は食欲減退色と言われますが、ここまで青いとかえって美しく見入ってしまいます。(直接食べる部位でもないので尚更)
南方のブダイは発砲の蓋を開けたときから海藻のような独特な香りが漂ってきて、実際食してみても皮目からそのような香りがしてきます。
しかし今回のナンヨウブダイは捌く前からその香りが感じられず、湯引きの調理で湯をかけた際にもほぼ無臭。
おやおやこれは…?と期待をしながら一切れ。

これは美味しい。文句なしでブダイで一番うまい。
クセがここまでないブダイは初めて食べました。
だいたいどの種も、海藻のような独特な香りを感じますが、ナンヨウブダイにはそれがありません。
今回の個体がいいのか、処置が素晴らしいのか。はたまたナンヨウブダイという魚はこれが普通の味わいなのか。
初めて食べたものなので、この魚は美味しい!なんてデタラメは言えませんが、少なくともこれまで食べたブダイ科魚類ではトップを張れます。
ナンヨウブダイの美味しさを最大限味わうには、数種類のブダイを食べ巡って来てからの方がいいかも知れません。

皮がなくても食感のある身を噛みしめると甘味が漏れてくる。
夏の活魚のメイチダイをどこか思い出します。
味を具体的に説明すると言葉が見つかりにくいけど、確かな旨味がある。
舌にのせてすぐは味が味覚として伝わらず、体温で馴染んできてからは甘さが感じられるようになります。
百聞は一見に如かずという言葉をここでこそ使いたい、文字に書き起こすのが難しいが、質・味ともに間違いなく美味しい魚です。
ナンヨウブダイの握り

ナンヨウブダイは刺身用に取った柵から寿司ネタように大き目にスライスする。
皮なし、湯引きを用意しました。
先に食べた刺身ほどの感動はありませんが、薄く切ると柔らかさが目立ち、シャリと馴染む様子が分かります。
シャリと合わせることでブダイの味が引き立ち、シャリと合わさっても感じられる上品さ。
特有の香りが全くと言ってもいいほどになく、他の魚らしく思えます。
南方の砂地に生息する大型のフエフキダイ科らしいしっとりした密度の高い硬さのある食感と、ほんのり感じる甘味。筋肉の繊維までもが似ています。
皮は比較的柔らかく、湯引きはほんの僅かな食感が加わったな。という程度で、身の重厚さの影に隠れてしまう印象です。
血合い筋も殆どなく、皮を引いてしまうと真っ白で殺風景な見た目なので見栄えを気にしたい場合は湯引き、ピンク岩塩など色付けをしてつけるのであれば皮引きで。が一番使いやすいでしょうか。
より皮の面積が大きくなる切り方をすれば食感が目立ち、変わった印象になるでしょう。
風味自体に変化は特に見られなかったので、有無は使い手次第で良いかと思います。
ナンヨウブダイのバター焼きとウロコチップス

ナンヨウブダイは骨つきでソテーする。
味つけにハーブ類、塩、少量のカレーパウダーと小麦粉をまぶせばあとはバターでソテーするのみ。
香付けにオリーブオイルも仕上げに垂らします。
バターの香りが旨味や脂らしさを補い、上品な身の野性的な美味さを引き立てる。
尾に近い部位なので味も比例して濃いところになります。
火が通り、生では感じられなかった味がこちらは味わえ、また異なった印象になります。
鱗チップスも簡単。
剥がした鱗は塩水を作り漬ける。
表面側の滑りが残っている場合があるので流水で念入りに落とす。
綺麗になったら素揚げにする。
油に浮かんできたら取り上げて油を切り、塩コショウなどお好みで味付けをする。

南国の魚の身はバターと相性が良く、上品な味をバターは白身らしさを引き立て、立体的に組み立ててくれる。
ソテーしても身に水分がやや残るので皮と骨を取って調理しても良いでしょう。

チップスは鱗が筒状に丸まり、パリンっと弾ける食感が楽しい。
これに味という味はないけれど、パンチのある香ばしさがあとを引くところなどつまみにするにはもってこいな一品。
ブダイ類はみな大きなうろこを持つので
ナンヨウブダイの尾鰭の唐揚げ

鱗は落とさずにとっておき、塩コショウで味付けし小麦粉をまぶして揚げるだけの簡単なもの。
可食部、というより肉と鱗のある部位を大きめに落としてお造りの飾りとし、当然これをそのまんまポイッと捨ててしまっては勿体ないので揚げてみました。
そんな気まぐれで調理したものですが、これが美味すぎる!
松笠焼きにするには鱗が頑丈なので、揚げてしまうのがブダイの鱗を活用する調理としては有効です。
頑丈な尾鰭の骨の周りに纏った肉は僅かしかありませんが、魚の味が十分にあり、鱗の香ばしさとパリッとした食感が自然と衣のようになり、香ばしいフライのようになります。
尾鰭は意外に硬く齧りきれないものでしたが、鱗・尾の肉だけでも特をした気持ちになれます。
ナンヨウブダイの評価
価格 ・・☆☆☆
コスパ ・・☆☆☆
珍しさ ・・☆☆☆
味わい ・☆☆☆☆
価格
・沖縄で漁獲されるイラブチャー(ブダイ科)の中でも最も高いもの。BOXに入れていただいていたが、本来入るようなものではないと思われる。
コスパ
・頭が大きいが魚体は大きいので身の可食部が多い。
珍しさ
・沖縄など琉球列島で主に水揚げされる魚。都内はもちろん、本州などで探してもそうそう見つからない。産地で入手する必要がある魚。
味
・上品な味わい。ブダイ類に感じられる皮目の独特な香りが殆どなく、万人が食べやすいような味。沖縄で揚がるいらぶちゃー(ブダイ科魚類)の中でも味が良いとされる。沖縄は高校時代に行ったきり。数年行けていないため、現地での鮮魚の扱いや各種に対する評価など調べに行きたいところ。
今回はナンヨウブダイを初めて頂きました。
非常に美しい魚体を手に取り間近で観察できただけでなく、ブダイ類の中でもトップクラスの味わいで非常に満足感が高い1尾でした。
気になるブダイ科といえばあとはカンムリブダイ、イロブダイといったやはり南方の大型種たち。
ナンヨウブダイに負けず劣らずな魚か、はてまた異なる美味しさのものなのか。

副管理人:夢海 未利用魚の有効活用方を探して、様々な魚種を食べて美味しく食べられる方法を研究しております。今まで550種以上の魚類を食べてきました。変わった魚の食べ方を中心に公開させて頂きます。どうぞよろしくお願いします! Twitter: @YUMEUMI27 ブログ: 夢海のまったり魚日記
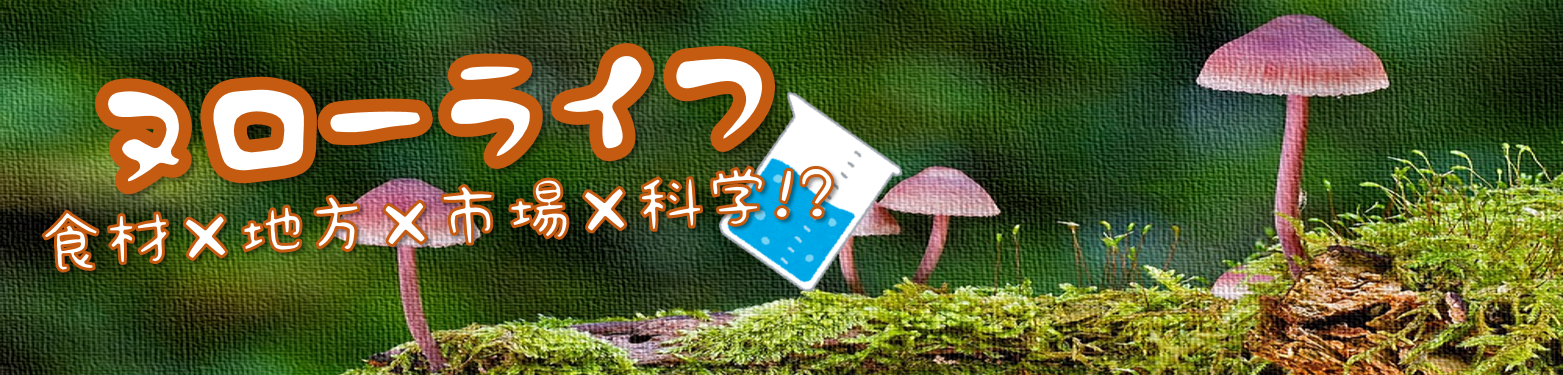


ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません