ねずっぽ3種の食べ比べ
こんにちは、夢海です🐟️
今回は3月初めに生牡蠣が理由であろう胃腸炎に苦しめられ、2日半ほどダウンしていました。
そんな病み上がりで徘徊した市場で見つけたのは茨城県平潟港で揚がったという、"めごち"であり"ねずっぽ"である。
紛らわしいのでタイトルは"ねずっぽ"で、文中では個人的に言い慣れた"めごち"と紹介する。
ちなみにメゴチという魚も存在するものの、こちらは正真正銘コチ科の魚であり、ネズッポ科の別称"めごち"とは関係がないので注意。

↑コチ科メゴチ
さて、買い求めてきた"めごち"は、やや小ぶりではあるものの、通常のネズミゴチのほかに何かしら混ざっているなと感じ取り、大きめのところを10本買い求めてきました。

持ち帰ると同定大会が開催されます。
ネズッポ科など、特に種類間の見た目が酷似しており、鰭を開いて模様を確認したり、棘の形状を見なくてはなりません。
ネズッポ科をじっくりゆっくり見る機会は数年前に購入したセトヌメリを調べた以来の事。
久しぶりに検索図鑑でネズッポ科のページを開く。
ネズッポ科は鰭を閉じていると見た目が酷似しており、"めごち"と一口に言っても複数種いることを知らないと、そのまま"めごちという魚だ"と、一蹴してしまうことでしょう。
今回購入した10本のうち、6本がヌメリゴチ(雌雄3:3)、残り4本がネズミゴチの雌でした。

↑ネズミゴチ雌
今回見た種類の中では唯一臀鰭が白いため、お腹から見るだけで判別ができる。

↑ヌメリゴチ(雄上、雌下)

こちらは雌雄共に臀鰭が黒いので、ネズミゴチと判別が容易であった。
複数種混ざっていると思ったものの、雌雄の違いもあるため実際には2種のみ、でした。
ネズミゴチ科の魚は雄雌で見た目が異なる種もいるため、余計にややこしい事が分かると思います。
さらにこの翌日、箱をもう一度見てみると明らかに模様が違う個体が混ざっているのに気がつく。


同定をした直後なので特徴が捉えやすく、こちらも購入し持ち帰ると、今度はヨメゴチであった事が分かる。
本来であれば尾鰭の長い種ですが、トロールで漁獲されたものであるため、尾は半分ほどに折れていました。
目次
めごちの料理
めごちの天ぷら(ネズミゴチ、ヌメリゴチ、ヨメゴチ)

まずはネズミゴチ。
こちらは食べなくても分かる、正確に覚えてはいないが実に7年越しくらいにはなるかな。
なんならキスよりも美味いじゃない。と、狙いで釣っていたシロギスの外道である筈が、本命よりも嬉しいゲストという立ち位置を小学生時代の私の中でも確立していた。
以来市場で見かけはするものの、1個人の晩のおかずになるだけなので、5.6本あればいいや。しかしこれだけを買うのに手を止めてしまうのが申し訳ない。となかなか買えずにいたのだ。
話が逸れたので天ぷらに話を戻す。
軽いのに、太いから味がよく分かる。
ああ、今食べているのは白身だ。と分かるけれど、淡々とした白身ではなく、食べるたびに広がるような旨味を一歩一歩踏みしめながら歩いているみたいだ。
これっぽっちの魚なのに味に深みがある。
塩がさらにコクを増し、深みを出してくれる。
一方のヌメリゴチ。

1個体は外れで捌いた時に気になったガス臭い個体が混ざっていた。
個人的には食べられないわけではないものの、気になる人は気になるだろうな、というものなので、初めて食べる人にこれを食べさせてはいけないものである。
残念ながら一定数こういった個体はいるため、一度食べて美味しくなかったって、めげずに食べて欲しいところです。
すると必ず美味しいものにぶち当たってくる。
ヌメリゴチはどの個体もネズミゴチよりやや小ぶりであった為か、旨味がやけにスッキリしているように感じる。
身の硬さもネズミゴチは筋肉の節がそれぞれ固まるのに対し、ヌメリゴチは全体をぎゅっと圧縮したような印象。
ホロロッとした旨さに対する感動が、ネズミゴチの後ではイマイチ沸かない。
先に食べるべきはヌメリゴチであったかもしれない。

ヨメゴチはこれまた旨味豊か。大型になる本種の中ではまだ小ぶりなものの、ネズミゴチに匹敵する。
大型のものは、今回購入した単価の4.5倍は付くのも納得である。
各種、基本的にはしっとりした質感ではあるものの、満足感が強かったのはやはりネズミゴチ、ヨメゴチであった。
今回の荷がヌメリゴチ主体で小ぶりだった為か、ややお買い得に感じられた。
ヌメリゴチ、ネズミゴチの一夜干し

めごちを購入して来たことは殆どなく、幼い頃に釣ってきた時も"揚げると美味いものだ"という認識でしかありませんでした。
今回はこれを一夜干しにする。
頭と内臓を取り除き、滑りを取ったら塩をする。骨の除去は不要。
あとはこれを冷蔵庫、もしくは朝晩は寒い時期であれば外干しでも◯、で乾燥させる。
表面が乾ききらず、しっとりとした状態のものを焼き上げる。
小さいのでガスコンロの中火で5分もあれば美味しく焼き上がります。

ネズミゴチ
まずネズミゴチから。僅差ではあるものの、魚体が少しだけこちらの方が大きく、食べ応えも感じられた。
皮が付いているので片身がホロロっと骨から素直に外れて、実に身離れがいい。
これをさきイカの如く手でむしりかじる。
干物で食べるのは初めましてなのに、どこか懐かしい面影が感じられるのは、しばらく食べていないキャペリンの方のししゃもなんかを思い浮かべた為だと思う。

ヌメリゴチ
天ぷらではネズミゴチにやや劣ると感じられた本種も、干せば味が凝縮されてネズミゴチと張り合える。
小ささ故に、なのかも知れないが、天ぷらで他種との比較を持ちかけてしまうと、大人しく干物にした方が良いのかもしれない。
あまりに小さいめごちは、チマチマ開いて粉を付けて揚げるよりも、ヌメリを取って塩をして干しておいた方が、労力的にも飲食店には扱いやすいんじゃないかな〜と。
生もののめごちを扱う天ぷら屋なんて今時高級店でしか見たないようなものなので、一夜干しだと聞こえもよく、敷居が低くなり手頃につまみやすくなる。
めごちの評価
・ヌメリゴチ
価格 ・・・☆☆
コスパ ・・・☆☆
珍しさ ・・☆☆☆
味わい ・☆☆☆☆
・ヨメゴチ
価格 ・☆☆☆☆
コスパ ・・・☆☆
珍しさ ・・・☆☆
味わい ☆☆☆☆☆
・ネズミゴチ
価格 ・・☆☆☆
コスパ ・・・☆☆
珍しさ ・・・☆☆
味わい ・☆☆☆☆
・価格
今回、サイズが近しく入会で来たものの、大型にならないヌメリゴチは安いものだと思う。一方で掌を超えるほどの大型のネズミゴチ、ヨメゴチは、養殖本マグロと張れるほどの単価が付くこともある。ネズッポ科は総じて小さければ安い、大きいと高い、そういう認識であながち間違いはない。
・コスパ
小型でありながら頭が大きいため歩留まりは良くない。しかし余計な小骨等は少なく、卸して中骨を取ればあれこれ使える。焼くのであれば中骨はあってもいい。
・珍しさ
流通上初めて見たのは3種のうちヌメリゴチのみ。小 型なのでよほど魚がない時期でない限りは流通してこないものだと思う。ネズミゴチ、ヨメゴチは何度か見ている。ヨメゴチの方がやや少ない。
・味
総じて白身らしさのある旨味が強く、特に大きいものほど美味い。鮮度がいいと刺身にも。
今回は病み上がりに見つけた"ねずっぽ"を食べ比べしてみました。
ネズッポ科は普段手にすることが少なく、当然飲食店でも見かけません。
今年の夏は釣りに行くかな、なんてぼんやり考えさせてくれる魚でした。

副管理人:夢海 未利用魚の有効活用方を探して、様々な魚種を食べて美味しく食べられる方法を研究しております。今まで550種以上の魚類を食べてきました。変わった魚の食べ方を中心に公開させて頂きます。どうぞよろしくお願いします! Twitter: @YUMEUMI27 ブログ: 夢海のまったり魚日記
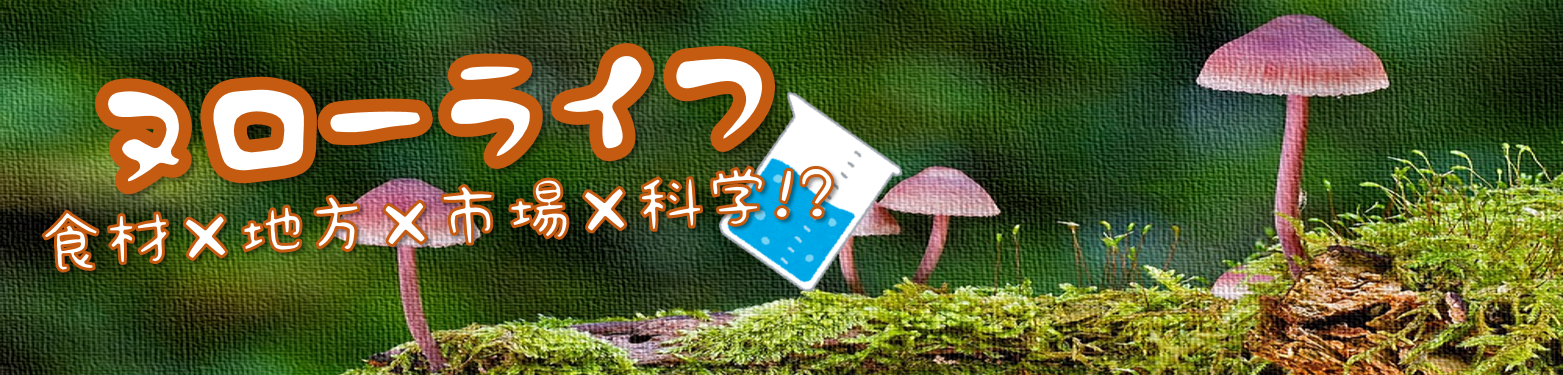


ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません