三重から貝の色箱がやってきた!
こんにちは、夢海です🐟️
毎日市場に入り浸っては水産物を眺める日々で、今年は魚類に限らず貝類なども多く見てきました。
すると色々面白い発見も身近にゴロゴロ転がっている事に気づき、より市場流通するものへの解像度が上がる年になったのではないかと思えます。
今回、三重県から来たというサルボウの荷を覗き込んでみると、どうも多種多様で面白そうな箱が来ていました。
目次
多種多様な三重県の貝たち

サルボウはたまに市場で見かけると言った程度。愛知県産の青いネットに入れられているのを見かけますが、水に浸かっているサルボウというのは今回初めて出会いました。
面白いと箱に顔を近づけ、水中の貝を見ていると、白くミゾが深い貝殻で、縦に向かって放射を描く特徴のサルボウにしてはおかしいと違和感に気が付きます。
まじまじ見ていればサルボウらしからぬ、らしからぬどころではないほど似つかない貝がチラホラ...
水からすくい上げると明らかにサルボウではない2枚貝が多いことに気が付きます。
さすがに5kgの箱を中身全て見るなんて事はできませんでしたがおおよそ半数はサルボウ以外の”混じり物”でした。

この中から欲しい物を選び持ち帰りました。
如何にも貝好き、生き物好きが潮干狩りで持ち帰ってきそうな色とりどりの貝を台所に並べると市場ではなく潮干狩りから帰ってきたような感覚となります。
幼稚園で訪れた富津の潮干狩りで、(記憶の中では)カタクチイワシか、アユの稚魚かといった銀色の小さい魚をバケツに入れて持ち帰ったことが記憶にあります。
”三つ子の魂百まで”なんて、そう思えば幼少期から変わらず生き物が好きであるという事は自分の中でも数少ない誇れるものなのだと思えます。

みな地味な色味だが見慣れない形の貝にワクワクする。

まずはこちら。
円を描くような輪肋は放射肋のサルボウとは異なり違いが目立つ。
恐らくはカガミガイであろう。なんて思うが自身なし。
稀にカガミガイとして単体で入荷することもあるので、非常に珍しいなんて事はなさそう。

こちらも恐らくはカガミガイ。
色味が異なるのは大きさのせいなのか。

こちらがサルボウと思われるもの。
これが主役のはずの箱だというのに、5割ほどしか入っていなかった。
身が赤いので生きて口を開けているものは他の貝と目立って違いが分かる。
愛知など他産地のサルボウはより殻が白く黒の面積は少ないように思える。
サルボウとされるものの中にも複数種混ざっているのかもしれない。

これはオニアサリと思われるもの。
本種とカガミガイらしき貝が混じり物の半数を占める。
名前こそ知っていたが実物を見るのは初めて。
貝殻が厚く丸みがあり、小粒の割に重みが感じられる。
身が詰まった様子からいい身が入っていそうでおいしそうに感じられます。

ツメタガイ
この箱の中に1つだけ紛れていた、唯一の巻き貝。
2枚貝の殻に穴を開け中身を捕食することでも知られ、アサリなどを捕食する貝としても知られます。
長いこと食べてみたかった本種をまさかこの箱で見つけることになるとは思いもしませんでした。
身は縮こまり辛うじて生きている状態。早めに調理する方が良さそうです。
三重の多様な貝を実食
三重県産2枚貝の酒蒸し

各種2、3個ずつ持ちかえったのでまとめて酒蒸しに。
砂抜きは気持ち程度に、水洗いして蒸していきます。
以下はそれぞれの食味の感想を書き綴ります。

カガミガイは殻に対して身が一番小さかったが、食感が良かった。
控えめな貝の旨味はサラガイ(白貝)などが一番近いように思えます。
あっさりした味は酒蒸しにして無心で食べられるうまさがあり好きな貝の一つです。

小型の殻が白いもの。
こちらの方が殻に対する身の割合が大きかったり、水管も長い点などやはり別種を疑ってしまう。
食感や味は似ているものの、こちらの方がより味は薄い気がします。
サルボウ

赤い身でこの中では目立ち、貝殻を見なくともわかる。
旨味は中間的。貝らしい風味は弱い。
どちらかと言えば佃煮など、醤油など味を付けながらで柔らかく煮るのが美味しそうであると思える大きさに柔らかさ。
実際、古くから干潟近くの地域ではそう食べられていたのでしょう。
古く江戸でも恐らくは広く食卓に上っていたのだろうものだが、江戸前のものはおろか、サルボウ自体毎日は見かけない。
もっと広く味を知っておきたい貝の一つです。

オニアサリと思われるもの。
身の厚み、味の濃さはこれが一番強かった。
が、舌に痺れが感じられる。
ビリビリとハッキリしたものではないですが、何となくイガイガチクチクとした刺激が感じられます。
話には聞いていたので”ああ、これか。”と冷静になれたものの、この前情報がなければ悪い物でも食べたんじゃないか。なんて思えてきそうです。
味は間違いなくアサリ以上。今回の個体は旨味の強さが貝類でもトップクラスでした。
系統はハマグリの澄んだ味わいよりもホンビノスのようなパンチのある印象。
身は痺れるので、出汁の加工品等に活用できるのではないかと思います。
今回は3玉のみ食べましたが、オニアサリのみ買い集めて冷凍したらどうか、火の入れ方を変えればどうなるか。等、試してみたいことだらけです。
ツメタガイの塩ゆで

ツメタガイは塩茹ででいただきます。
干潟で見かけたり、貝殻もよく目にする種類でしたが実食は初めて。
身はシャクシャクした食感で磯の貝を象徴するような印象で、尻高貝のそれに近いものを感じました。
肝はほんのりした苦みが身に対しての大きさからも食べやすく、個人的に評価できる点です。
刻んで出汁で炊き込む、甘く煮る、軽く湯がき握りにする。等でも美味しく味わえそうであると感じました。
ツメタガイも今後探さなくてはならない水産物となりそうです。
まとめ
今回は複数種が混じっていた三重の貝を頂きました。
近年では貝類全般の不漁など、見られる種類は少なく、細くなってきてしまっていると感じられるこの時代で貴重な経験が出来ました。
貝を同時に何種も食べ比べるなんてやろうと思っても難しいのではないでしょうか。
もちろん、食べ比べると言っても”つぶ貝とホッキ貝”、”アサリとホタテ”のようなあまりにかけ離れたものは除外しての話で、です。
三重や愛知などは一般的に食用とする貝の種も多いですが、今回のようにあまり流通しない種類も混じりでやってくるほど興味深い地であることが分かります。
三重は鳥羽や志摩などを水族館の目的で何度か訪問していますが、水産という視点ではまだどこも見れていないのでいずれ水産を巡る旅で紀伊半島をぐるっと一周してみたいものです。

副管理人:夢海
未利用魚の有効活用方を探して、様々な魚種を食べて美味しく食べられる方法を研究しております。今まで550種以上の魚類を食べてきました。変わった魚の食べ方を中心に公開させて頂きます。どうぞよろしくお願いします! Twitter: @YUMEUMI27 ブログ: 夢海のまったり魚日記
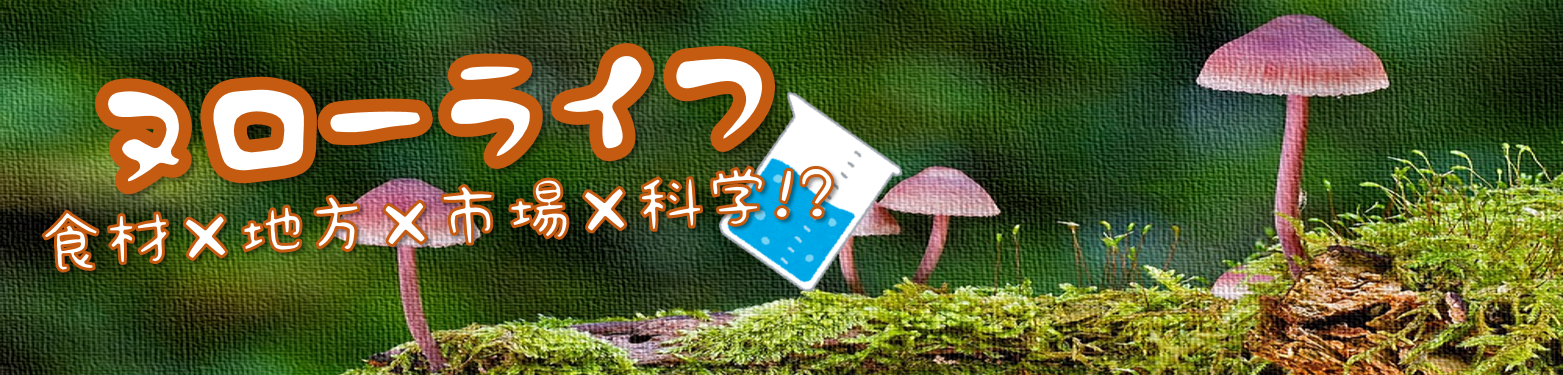


ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません